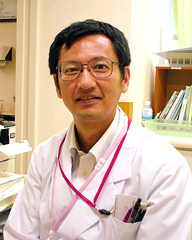厚生会クリニック
クリニックのご案内
内科全般
日常生活の中で感じる身体のトラブル、検診などで指摘された項目に対する精密検査、治療など何でも気軽にご相談できる、それが地域でのホームドクターとしての役割です。
厚生会クリニックは、皆様のホームドクターとして診断・治療・説明いたします。

感染症対応の診療体制について
当院では、外来において受診歴の有無に関わらず、発熱・呼吸器症状・消化器症状またはその他の感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受け入れを行うために必要な感染防止策として、それらの患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有して診療しております。
帯状疱疹ワクチンのご案内
★クリニックでは、シングリックス(不活化ワクチン)となります★
帯状疱疹ワクチンは50歳以上が対象のワクチンです。
(80歳までに約3人に1人が発症してると言われています。)
- シングリックス金額は?
- 1回目:22,000円 2回目:22,000円
合計:44,000円。
- シングリックスの効果は?
- 2回接種で十分な予防効果!!!
必ず2回接種しましょう。
- シングリックスの接種期間は?
- 期間:1回目接種後2ヶ月あける
(遅くとも6か月後までに接種する)
50歳以上であれば、どなたでも接種可能です。
詳しくはクリニック受付までお問合せ下さい。
厚生会クリニック診療予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医科 | 午前 8:30~12:00 |
一般外来 | 安田 悟 | 安田 悟 | 安田 悟 | 安田 悟 | 安田 悟 | - |
| 血管外科 | 安藤 精一 (第3) |
- | - | - | - | |||
| 午後 12:00~17:00 |
一般外来 | - | - | - | - | - | - | |
| 整形外科 (予約制) |
- | 千葉 勝実 (2ヶ月に1回) |
- | - | - | |||
| 訪問診療 | 林 高太郎 | 林 高太郎 | 林 高太郎 | 林 高太郎 菅野 優紀 |
林 高太郎 菅野 優紀 |
|||
ドクターコラム
厚生会クリニック 院長 安田 悟
皆様、こんにちは。地域の皆様方には、日頃より大変お世話になっておりまして、誠にありがとうございます。
さて、「健康寿命」という言葉を知っていらっしゃる方も多いことと存じます。これは、2000年にWHOが提唱した概念です。平均寿命が、寿命の長さを表しているのに対し、健康寿命は、日常的・継続的な医療や介護を必要としない、自立した生活ができる期間を意味しています。
残念ながら、平成25年の統計によれば、平均寿命と健康寿命には、男性で約9年、女性で約13年の差があります。つまり、この期間は、自立度が低下し、医療や介護が必要となるということになります。
「元気で、長生き!」という言葉がありますが、できるだけ健康寿命を伸ばし、できるだけ長く、自分らしい、生き生きとした生活を送りたいものです。このためには、バランスのとれた日々の食事や、適度な運動の継続がとても大切になると思います。
食事については、減塩を心がけ、野菜の摂取量を増やし、お肉、お魚などの良質のタンパク質をしっかり摂ることが重要です。当院では、管理栄養士による食事指導も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
ドクター紹介
- 安田 悟 Satoru Yasuda
厚生会クリニック 院長
| 診療科目 | 内科 訪問診療 各種検診 |
|---|---|
| プロフィール | 昭和62年 福島県立医科大学卒業 福島県立医科大学 第2内科入局 平成6年 福島クリニック(内科)勤務 平成13年 福島第一病院内科勤務 平成19年より 厚生会クリニック 院長 平成24年より 福島第一病院内科勤務 平成26年より 厚生会クリニック 院長 現在に至る |
| ひと言 | 地域の皆様に親しまれ、様々なニーズに対応できる、親切・丁寧なクリニックを目指すよう心がけています。 お気軽にご相談下さい。 |
保険医療機関における掲示
- 医療DX推進体制整備加算
- 医療情報取得加算
- 一般名処方加算について
- 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書
- 指定医療機関
- 施設基準の届出について
- 長期収載品の選定療養について
- 保健医療機関
- 保険外負担に関する事項
※掲示内容は予告なく更新する場合があります。
訪問診療のご案内
通院できなくても大丈夫!
医師が定期的にお伺いいたします
「訪問診療」とは?
医師の診療を定期的に受ける必要があるけれど、通院が難しいという方に対して、医師が予め診療計画を立て、定期的にご自宅に伺い診療を行うことを『訪問診療』といいます。
症状に応じて頻度に違いはありますが、原則月2回以上の訪問となります。訪問スケジュールは前月にお知らせしております。
検査が必要な時、症状悪化時は当クリニック受診や、協力病院対応にて治療となります。
診療内容
- 症状、全身状態の観察
- 在宅における創傷処置、膀胱洗浄、導尿、留置カテーテルの処置に関する指導管理など
費用
訪問診療は保険診療です。診療に関してお支払いいただく金額は健康保険による一部負担金となります。
通常の外来診療と同じようなものとお考えください。
訪問にかかる交通費は別途お支払いいただきます。
その他
- 適宜、健康保険証、重度心身障がい者医療費受給資格者証、介護保険証などをご確認させていただきます。
- 定期薬の薬局処方については、医師・看護師に御相談ください。
- 訪問診療と併用して在宅サービス(デイケア、ショートステイ等)をご利用の方はケアマネージャーとご相談ください。
- 「訪問診療」と「往診」は同じですか?
- 同じではありません!異なります
患者様の求めに応じて(呼ばれて)医師が出かけていくのが「往診」です。
当クリニックで行っているのは、診療計画を立て、医療的管理に基づいて、定期的にお宅に伺う「訪問診療」です。
訪問診療・訪問看護依頼書のダウンロードはこちら
ドクター紹介
- 林 高太郎
(はやし たかたろう)
訪問診療室 医師
| 出身 大学 |
埼玉医科大学 |
|---|---|
| 担当 | 訪問診療 |
| 資格・学会等 | 日本麻酔科学会 麻酔科標榜医 日本在宅医療連合学会 |
| ご挨拶 | 患者様、ご家族様とのコミュニケーションを大切に診療を行っていきたいと思います。どんなことでもご相談ください。 |
- お問合せ・お申し込み
- お電話でのご相談は
024-552-5315 までどうぞ
メールからもお問い合わせ頂けます。
人間ドックのご案内
| 8:30~ 11:00 |
受付・オリエンテーション
|
|---|---|
| 11:30 | 医師の問診および結果説明 栄養士による生活指導 軽食 |
| 12:00 | 終了 |
- 41,800円(税込)
厚生会クリニック
人間ドックの特徴
ABPI(血管年齢検査)を検査いたします。
これらは、臓器障害が発症する以前に動脈硬化の進展を簡単に評価するスクリーニング検査です。
人間ドックは健康診断ではわからない、病気の早期発見・早期治療と予防を目的としており、個人の意思によって受診するものとなります。一般的な健康診断よりも検査項目が多くなっています。
- ABPI検査機器
- お問合せ・お申し込み
- お電話でのご相談は
024-552-5315 までどうぞ
メールからもお問い合わせ頂けます。
健康診断のご案内
市民検診
健康な生活を送るために、年一回定期的な市民検診をお勧めします。
検診を受けることによって、自分の体の変化をいち早く見つけ生活習慣病の早期発見や予防ができます。
| 期間 | 毎年6月1日~10月31日 |
|---|---|
| 検査項目 |
|
企業検診
企業健診は35歳以上を対象とする生活習慣病予防健診と労働安全衛生法に基づき、年に一度の定期健康診断があります。
(健康診断とは受ける方の年齢に応じた一般的な検査のことを言います。)
| 期間 | 随時 |
|---|---|
| 検査項目 |
|
特定健康診査・特定保健指導について
日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病の生活習慣病の有病者・予備軍が増加しており、それを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。
生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導を積極的に利用し、バランスのとれた食生活、適度な運動週間を身に付けましょう。

対象者
医療保険に加入している被保険者(本人)・
被扶養者(ご家族)(政府管掌健保・組合健保・共済組合・国保)
40歳~74歳までの全ての方が対象となります
特定健康診査とは?
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。
| 基本的な項目 |
|
|---|---|
| 詳細な項目 |
|
特定保健指導とは?
特定健康審査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。
(よりリスクが高い方が積極的支援です)
| 動機付け支援 | 積極的支援 |
|---|---|
| 初回面接:個別面接20分以上。 専門的知識:技術を持ったもの(医師・管理栄養士等)が、対象者に合わせた実践的なアドバイス等を行います。 |
|
| ご自身で、「行動目標」に沿って、生活習慣改善を実践 | |
| 面接・電話・メール・FAX・手紙等を用いて、生活習慣の改善を応援します。(約3ヶ月以上) | |
| 実績評価:面接・電話・メール等で健康状態・生活習慣(改善状況)を確認(6ヵ月後) | |
保険者・代表保険者
国保事業者・民間保健指導事業者さまへ
- その他、各種検診・人間ドック等、両施設とも実施いたしております。
- お問い合わせ
- 厚生会クリニック
024-552-5315
ワクチン接種のご案内
インフルエンザ予防接種(10月より接種可能です!!)
| 注射タイプ | 12歳以上(中学生以上) | 4,000円(税込) |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 1,500円(税込) | |
| 点鼻タイプ(フルミスト) | 12歳(中学生以上)~18歳以上 | 8,000円(税込) |
| 接種実施日 | 月曜日~金曜日 | |
| 時間 | 13時30分~16時30分まで | |
※フルミストは、鼻にスプレーするタイプです。
ワクチン効果は、注射タイプが「約5ヶ月」に対し、「約1年」と長く効果が期待できるのが特徴です。
※ゼラチンアレルギーのある方、重い喘息のある方または喘息の症状がある方は、予防接種を受ける際に医師と相談ください。
- 予約受付
- 電話または受付窓口にて予約受付しています
024-552-5315
予防接種料金表
| ワクチンの種類 | 税込金額 |
|---|---|
| インフルエンザワクチン | 4,000円 |
| インフルエンザワクチン点鼻薬(フルミスト) | 8,000円 |
| コロナワクチン | 15,000円 |
| MRワクチン(麻疹と風疹の混合ワクチン) | 12,100円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 7,700円 |
| 肺炎球菌(プレベナー) | 9,900円 |
| ツベルクリン反応(判定料込み) | 4,400円 |
| HB肝炎ワクチン | 7,700円 |
| HA肝炎ワクチン | 8,800円 |
| 破傷風トキソイド | 5,500円 |
| 3種混合(破傷風・百日咳・ジフテリア) | 7,700円 |
| 2種混合(破傷風・ジフテリア) | 7,700円 |
| 乾燥弱毒性水痘ワクチン(生ワクチン) | 9,900円 |
| 高齢者帯状疱疹ワクチン(シングリックス) (2回接種となります) |
1回 22,000円 |
| 高齢者帯状疱疹ワクチン(生ワクチン) | 9,900円 |
- 上記は、診察料・接種手技料及び判断料、税込みの価格です。
- 予防接種は、全て予約制となりますので、予めご了承下さい。